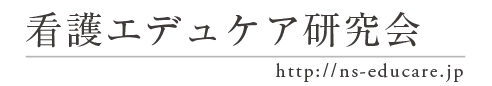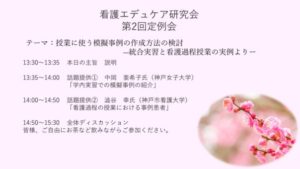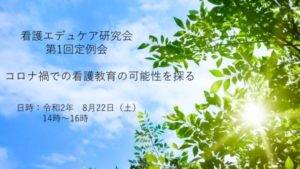2021年度の定例会は、今回が第1回目です。話題提供者を含めた合計15名で、Zoomを使っての開催となりました。テーマは「あらためて基礎看護学を考える」です。
現在、世間はコロナ一色で、看護基礎教育も継続教育も大きな影響を受けています。また、地域包括ケアや地域創成事業の推進などの社会情勢の変化からの影響も受けています。2022年4月からは、看護基礎教育のカリキュラムが新しくなりますが、新カリキュラムにこの変化への対応を盛り込んでいる教育機関も多いことでしょう。看護教育はひとつの転換点を迎えていると言えます。基礎看護学は、かねてより看護基礎教育の中核をなすと捉えられてきましたが、これからの社会の期待に応える看護職養成において、どのように教授内容を捉え、実施していくべきか、さらには今後どのように変化していくべきか、このような問いをもって今回のテーマを設定しました。
話題提供をいただいたのは、千里金蘭大学看護学部、基礎看護学領域教授の登喜和江先生と、佛教大学保健医療技術学部看護学科、基礎看護学分野教授の山本直美先生です。先生方は、成人看護学を専門とされていたとのことですが、現在は基礎看護学を専門とされ、基礎看護学の教育的な意義や教育活動に面白さを感じているとのことでした。
登喜先生は、看護学概論で何を教えているのか、基礎看護学教員の経験の教材化について、基礎看護学は看護基礎教育の要になるかの3点についてお話いただきました。先生は、基礎看護学は入学したての学生を看護学に誘う科目であるとのお考えから、入学生が抱いていた看護へのイメージを良い意味で作り替えることで、看護を「面白い」「より深く知りたい」「看護を選んで良かった」と感じられることを大切にされているとのことでした。登喜先生のお話で一番印象に残ったのは、初学者に看護への興味関心を持たせる役割を担う基礎看護学の教員は、看護の魅力の発信者であること、看護実践者への敬意を払っていること、人間への関心、教育への関心を持てていることが重要だということでした。そして、基礎看護学は、看護基礎教育の最も重要な部分を支える教育を担うという点からも、医療や看護が高度化・専門分化することによる教育者の暴走、すなわち専門性の名の下に基礎教育を逸脱することがないよう、看護基礎教育の核を見失うことなく、あるべき姿に質すことが重要だとも言われました。激動の時代だからこそ、時代を見据えた看護基礎教育のあり方についての先生の深い洞察とこれからの基礎看護学教員へのメッセージが読み取れたお話でした。
山本先生も、初学者である学生にいかにして看護学への興味をもたせ自己主導的な学習ができるようにしていくのかを考えた授業をされていました。看護学概論ではポートフォリオの記入や闘病記やミルトン・メイヤロフの「ケアの本質」の読破など、学生を学問の世界に誘う工夫を様々にされていました。また、山本先生は、特に看護技術論の必要性についても述べられました。「コロナ禍でオンライン学習になることが多かったこの2年間、基礎看護技術演習を担当する教員の活動は授業中のデモンストレーションや学生への直接指導から、ビデオ教材作成に置き換わっているように思われる。しかし、本当にそれしかないのか、それで良いのか」という疑問も投げかけられました。また、現場のリアリティの追求としてのシミュレーション教育についても、リアルさをどんなに追求しても、本物ではないことを忘れてはいけないとも言われていました。
お二人の先生の話に共通していたのは、基礎看護学は、「学び方を学ぶ」科目であり、看護の楽しさを伝える科目であるということで、学生が楽しいと思える教育活動を行うことの大切さ、だったと思います。
お二人の先生の話題提供の後、参加者全員で意見交換しました。3年生の実習を担当している参加者からは、基礎看護学実習の時のようなピュアさが失われているような気がする、患者指導にばかり目が向いているような気がするなど、基礎看護学の学習で培った看護職者としてのアイデンティティや看護観が各分野の学習にうまくつながっていないのではとの疑問が出されました。登喜先生は、成人等の専門分野にはそれぞれの目的、目標があり、学生はそれに適応することもふくめて学習していること、それを経て看護師になっていくこと、基礎看護学の教育目標は、看護基礎教育の目標でもあり、それは4年間かけて目指されるものであること、さらに、もしも、各専門分野の教育の中で失われているものがあるとすれば、現代の看護基礎教育において、専門職になるために学生が捨てなければならないものなのかもしれない・・と示唆に富んだ回答をしてくださいました。
また、臨床の看護管理者からは、職場への不適応を起こしていた新人看護師への面談で、どんな看護がしたいのかを丁寧に聞いていったことで、離職を回避できた事例が報告され、「どんな看護がしたいのか」という「立ち返る場」をもっていることが、看護職としての強みになり、それを培うのが基礎看護学ではないかとの意見が出されました。
最後に、基礎看護学は、1・2年生のための授業を想定しがちですが、4年間通して看護基礎教育は行われるのであり、基礎看護学に限らず、どのような分野も4年間の、あるいはその後の看護師としての成長も視野にいれて教育を考えていく必要があることが確認されました。3年生、4年生、そして卒後継続教育においても基礎看護学分野の果たす役割がありそうです。今後もこの点を考えていきたいと思いました。
話題提供いただきました登喜先生、山本先生、ご参加くださった皆さまありがとうございました。