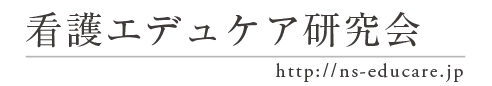今回のセミナーは、愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センターの内藤知佐子先生にご講義頂きました。参加者は、臨床から約20名、教育機関から約20名で、教育に携わる多くの方が関心を持っておられるテーマであることがわかりました。この参加者のニーズに合うように、講義は、学生・新人看護師との臨床での関わり方を含め、看護実践現場での発問や応答についてお話いただきました。
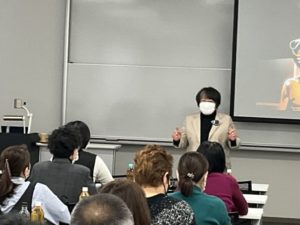
まず、内藤先生の講義は、アイスブレイクから始まります。先生はこの関連書籍も出版されていますが、アイスブレイクは、授業の導入で、学習者が楽しく自己開示し、緊張をほぐす活動です。それは学びに誘う準備として、学習者にとって安心安全な場が第一に重要で、内藤先生は本セミナーの導入でアイスブレイクを使うことで、セミナー参加者に体験的に伝えてくださいました。また、講義では参加者は2人1組になって学習する「バディシステム」で、様々な学習を楽しく体験しました。
講義は、Z世代の伸ばし方、心理的安全性、ファシリテーターになる、そして「発問」と「応答」のスキルの4つの内容でした。
Z世代の特徴は、他の世代(ベビーブーム世代、X世代、Y世代)との比較から始まり、コロナ禍を経験したZ世代の伸ばし方を学びました。Z世代を伸ばすには、チームに貢献できている実感をもてるように一緒に頑張ろうという姿勢で関わることや意義や意味を伝えて価値を見出すことが大切だということでした。
心理的安全性については、単に安心安全であるというだけではなく、責任の持たせ方と関連があることを学びました。心理的安全性が高くても、責任の度合いが低いと快適であっても「ヌルイ」と受け取られる場合があります。心理的安全性が高く、かつ適度の責任もある、そのことで、学習が進みます。
次にファシリテーターになるという点です。ここでは、指導する側から見える世界と学習者が見ている世界の違いについて、内藤先生が提示された写真をもとに体験しました。学習者がどんな世界を見て、何を体験しているのかをファシリテーターがまず受け止めることで、その違いを知った学習者の内省が自然に発生するそうです。何よりも学習者の持っている力を信じることが大事です。また、何がわからないかがわからない学習者もいます。その場合の振り返り方についても具体例をもとに体験させていただきました。


発問は、教育的な意図を持った問いかけです。適切な問いかけは、学習者の興味が喚起されたり、発想が広がったり、思考を深めたりします。内藤先生は、6つの発問と4つの応答があると言われます。授業の導入時には、導入の発問(〇〇について聞いたことはありますかなど)、展開では、発散と収束の発問(なぜそう考えたのか、聞かせてくださいなど)、深化させる発問(在宅看護は本当にハッピーなんだろうかなど、いったん良しとされたことをあえて問いかけるなど)、まとめではまとめの発問(今日はどんなことをしましたかなど)、その他、授業や研修での話し合いをマネジメントする運営のための発問(何をすればよいかわかりますか)も紹介いただきました。それぞれの発問について、参加者が場面を想像しながら考えることができました。
応答については4つ紹介されました。それは、待つ、聴く、確かめる、返すです。もっとも重要なことは、応答することで心理的安全性をつくることだと学びました。学習者の答えに、まずは「すごい!」「さすが!」など肯定的なリアクションをすることが大切です。これも、バディと学習者と指導者になって体験させていただきました。発問と応答はセットであり、応答が意外に大事であることに気づくことができました。
質疑応答では、話したくもない上司とどう付き合えばよいのかや、発問が正しい答えの誘導のようになっていること、できない部分が多い人をどのようにほめるとよいのかなどがあがりましたが、一つ一つ丁寧に回答していただきました。大切なことは、学習者の力を信じること、「なんでわかってくれないの」という怒りは、期待と実際のジレンマであり、こちらの弱さでもあるから、まずは「そうきたか!」「なんと斬新!」と受け入れること、それをちょっと楽しむことが大事だと教えていただきました。
内藤先生のご講義は、先生の軽快な話し方がとても楽しく、また、具体的な体験をたくさん用意してくださり、あっという間の2時間でした。バディシステムで活動したことで短時間でも参加者間の交流が深まったように思えたことも成果のひとつでした。
半日という短いセミナーでしたが、とても充実した学びになりました。参加者の皆さま、内藤先生、どうもありがとうございました。
投稿者「管理」のアーカイブ
令和5(2023)年 第2回定例会を開催しました
今年度第 2 回定例会は、京都橘大学の野島敬祐先生を話題提供者としてお迎えし、京都橘大学シミュレーションコモンズにおいて、同大学のシミュレーション教育をご紹介いただくとともに、実際の設備を見学し、これからの看護教育におけるシミュレーション教育について意見交換を行いました。
野島先生の話題提供では、京都橘大学のシミュレーションコモンズについてご紹介いただきました。ここは、臨場感を持たせるための映像音響システム、効果的なデブリーフィングを可能にする映像収録・配信システムを備えた総合的なシミュレーションルームです。特に、全壁面に病室や災害現場を投影できる壁面構成シミュレーターは映像や音響効果により、学生がその場の状況に没入して、学習課題に取り組むことが可能な設備でした。学生が臨場感を感じられる映像や音響が効果的に活用されることで、現場に行かなければ実現できなかった体験を、より安全な環境で学ぶことができ、なおかつ、それを繰り返し学ぶことができます。話題提供ではその授業実践例を多く提示いただき、シミュレーション教育の可能性を感じました。
野島先生は、入学初期の段階から「シミュレーションという学び方を学ぶ」必要性を話されました。シミュレーション教育は、その手法を活用することで、学生がお互いに学びあい、主体性が引き出される学習方法だと言われています。野島先生は、この手法で学習した学生たちが自由に意見交換するようになってきたと話され、学生の可能性を信じる野島先生の教育姿勢を感じました。

設備見学では、実際の使用場面を再現いただき、参加者の質問にもお答えいただきました。COVID-19 以降、多くの教育機関でシミュレーション設備が導入されていますが、効果的な活用には課題が多いようです。参加者同士でそれぞれがもつ課題意識を共有する時間となりました。シミュレーション教育はどのような設備を導入するかではなく、導入した設備を活用するための授業設計が重要です。野島先生から、基本は普段の授業や演習設計と同じであり、その中でも、必要な学習要素を精選する視点の重要さを教えていただきました。教育者としては、あれもこれも学んでほしいと学習要素を盛り込みがちです。その中で「そぎ落とす勇気」をもつことの大切さ、「学習者の身になって考える」大切さを改めて感じる機会となりました。シミュレーション機材の使い方ではなく、教育活動の基盤となる教材精選や授業設計の重要性を改めて学ぶ機会にもなりました。

これまでの演習方法に、シミュレーション教育という手法を取り入れ、それを当たり前の教育にするためには、教育者同士の理解も不可欠です。京都橘大学では、学内 FDとともに野島先生が各領域の演習支援を行いながら、学内のシミュレーション教育普及に尽力されているようです。野島先生のシミュレーション教育にかける熱意を感じるとともに、どのような質問にもおおらかに、オープンにお応えくださる野島先生のお人柄に触れ、シミュレーション教育の楽しさを教えていだく時間になりました。
野島敬祐先生、参加者の皆さまありがとうございました。
令和5(2023)年度 セミナーのご案内
教育現場で日々繰り広げられている「発問」と「応答」は、「発問」によって相手からの「返答」、「返答」に対しての「応答」、そしてまた「発問」と循環する対話です。
「発問」によって相手が自己の興味関心を明確にしたり、思考を整理したり、視点の転換をしたり、思考が深化したり…大事なスキルですが時に難しく思うこともあるのではないでしょうか?
今回のセミナーでは、効果的な「発問」と「応答」の能力について学んでいきます。
チラシはこちらから⇒2023年度看護エデュケア研究会セミナー
テーマ
「発問」と「応答」のスキル
-学生・新人看護師のニーズをとらえる-
講師
内藤 知佐子 先生 愛媛大学医学部附属病院総合臨床研修センター助教
日時
2024年2月18日(日)13:30~16:30(13:00~受付開始)
会場
神戸女子大学 ポートアイランドキャンパスF館3階304会場
会費
会員 1500円 一般参加者:3000円
※当日会場での支払い
定員
80名(先着順)
※本セミナーは終了いたしました。多くのご参加を頂きありがとうございました
令和5(2023)年度 第2回定例会のご案内
令和5(2023)年度 第2回定例会のご案内
第2回定例会を下記の通り開催いたします。
本テーマにご関心のある皆様のご参加をお待ちしております。
チラシはこちら → 2023 第2回定例会チラシ(最終)
テーマ
壁面構成シミュレーターを使った授業の実際-京都橘大学シミュレーションセンターからの紹介-
話題提供者
野島 敬祐 先生 (京都橘大学看護学部看護学科 准教授)
開催情報
日時:令和5年11月26日(日)13:30~16:30(受付開始13:00~)
会場:京都橘大学清優館シミュレーション・コモンズ
対象:看護教員・看護師(看護教育にご関心のある方はどなたでも)
参加費:会員 無料 非会員500円(当日支払い)
定員:30名(※定員となりましたら、申し込みを終了いたします。予めご了承ください)
第2回定例会は終了いたしました。ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
令和5(2023)年度 第1回定例会を開催しました
今年度は、コロナウイルス感染症も2類から5類に変更となったため、対面式で定例会を開催しました。
大阪公立大学院看護学研究科実践看護学領域看護学分野 看護技術学の講師 山口舞子先生から「VRシミュレーションを用いた授業デザインと評価について考えるー基礎的看護実践力の育成を目指してー」をテーマに実践報告をしていただきました。今回は、VR機器を持参いただき、参加者にもVRシミュレーションの実際の体験をしたうえで、ディスカッションも大変盛り上がりました。
最初に、山口先生のこれまでのご自身の教育経験の中で、近年学生達が、患者とのコミュニケーションを取りながら観察し、共感する力が低下していることや、与えられた事例患者からの情報収集により受け身的学習になっているために、基礎的な看護実践能力が育成できていないということに問題意識を持っていることを伝えてくださいました。そこで、山口先生は、今回看護実践能力を育むためにVRシミュレーションを用いた授業デザインを導入されました。まず、大阪府立大学看護学部(実践された2022年度時点、現大阪公立大学)の教育目標からどのように基礎看護技術教育の実際がデザインされ授業構築がなされているかを説明いただきました。ご紹介いただいた授業が、講義から演習を経て基礎看護学実習に向かうための教育的位置づけの中に計画的にデザインされていました。
具体的には、VRシミュレーション(VR学習)前の事前課題として2週間前に事例を提示したうえで、胸部・腹部のフィジカルアセスメントの講義を実施し、講義後に事前課題に沿ったVR学習を実施し、その翌週に基本手技を用いた胸部・腹部の身体診査の演習をおこなうという流れでした。この授業デザインにすることで、事前課題で考えてきたことを一旦VR患者から得られた情報と照らし合わせて、不足している情報が何か、必要な問診を考えたうえで、翌週の実際の身体診査における学習の動機づけを高めることを狙いとされていました。
既に同様のVRシミュレーションを取り入れた授業をされている参加者の方からは、授業のどこにVR演習を組み入れるかによって教育効果に影響することに示唆を得て、自部署での今後の授業デザインを検討する機会になったというご意見をいただきました。また、事例設定においては、例えば、他科目で看護過程に用いている事例にするなど学生のレディネスなどを鑑みることの必要性や工夫の余地もありそうです。さらに、VR学習を取り入れることで臨地実習では体験できなかった新たな技術習得も仮想空間の中で体験できる(例;ドレーン挿入中の患者・ガーゼ汚染の実際など)可能性もあるなど、今後のVR学習の可能性を含めて様々な意見交換がなされました。VRシミュレーションを用いる意義は、リアリティを感じさせることにあるといえます。ディスカッションでは、そのリアリティは、VRを用いているからこそ患者の重症度を感じることや、学生同士ではない状況での対象者とのコミュニケーションなどの要素があることを確認しました。加えて、VR学習によって、学生が今後遭遇する可能性のある場面への動機づけとなり、その時に慌てずに行動できる、患者の安全性を一番に考えるという看護職としての責任を感じることにもつながるのではないかという意見もあり、新たな気づきと学びを得たディスカッションとなりました。
授業後のVR学習の授業アンケート調査の紹介では、今回の学習目標に沿って「患者に何が起こっているかを考えることができたか」「臨場感をもって学べたか」「VR患者への問診や身体診査により、来週の技術演習を積極的に学ぼうという気持ちになったか」という質問に対して、ほとんどの学生が良い学習効果を得ていることが明らかになったとのことでした。しかし、基礎的な看護実践能力の育成にVR学習が役立っているのかを評価するためには、どのタイミングで評価をするのか、看護職として職責を問うことも課題ではないかという意見も出ました。
今回の学びが、今後の皆様の現場での教育プログラムへの活用の一助となることを願っております。ご参加いただいた方々に感謝申し上げます。
令和5(2023)年度 会員総会を開催しました
令和5年度看護エデュケア研究会 会員総会を下記の通り開催いたしました。
看護エデュケア研究会総会
開催日時:令和5年7月2日(日)16:40~17:00
開催場所:I-Siteなんば 2階S1
当日の会員総会の資料が必要な会員の方は、事務局までご連絡ください。
会員の皆さまへ:令和5(2023)年度会員総会の開催について
令和5(2023)年度 会員総会を下記の通り開催いたします。
日時:令和5年7月2日(日)定例会終了後
会場:I-Siteなんば 2階S1
議題
1.令和4(2022)年度 活動報告
2.令和4(2022)年度 会計報告
3.令和4(2022)年度 会員動向
4.今後の研究会の在り方について
5.その他
定例会に参加されず、会員総会のみに参加を予定される会員の方は、
事務局アドレス(kanri@ns-educare.jp)に、6月30日(金)までにご連絡ください。
令和5(2023)年度 第1回定例会のご案内
令和5(2023)年度 第1回定例会のご案内
第1回定例会を下記の通り開催いたします。
本テーマにご関心のある皆様のご参加をお待ちしております。
チラシはこちら → 2023 第1回定例会 チラシ
テーマ
VRシミュレーションを用いた授業デザインと評価について考える
-基礎的看護実践能力の育成を目指して-
話題提供者
山口 舞子先生(大阪公立大学大学院看護学研究科実践看護科学領域基礎看護学分野看護技術学 講師)
開催情報
日時:令和5年7月2日(日)14:00~16:40(受付開始13:30~)
会場:I-Siteなんば 2階S1
対象:看護教員・看護師(看護教育にご関心のある方はどなたでも)
参加費:会員 無料 非会員500円(当日支払い)
定員:25名
本定例会は終了いたしました。多くのご参加を頂き、ありがとうございました
令和4(2022)年度 第2回定例会を開催しました
2022年度第2回定例会をオンラインで開催しました。今回は、シミュレーション教育に積極的に取り組んでおられる千里金蘭大学 伊藤朗子先生に「看護技術教育におけるシミュレーション学習の実際 -ファシリテーションと評価-」というテーマで話題提供いただきました。
千里金蘭大学では、2013年からシミュレーション教育を取り入れておられます。シミュレーション教育の良いところとして、学生が安全な環境で失敗できる場であり、失敗から学ぶ中で関わっている学生全員でやり直しながら成長し達成感を得て学びをつかみ取れることであり、大切なことは、学生の「気づき」にあると話されました。
シミュレーション演習をどのようにデザインするのか、演習目標やファシリテーターの関わり方、患者状況の設定、ブリーフィング、デブリーフィングのポイントとしてお話しいただきました。入学後まだあまり臨床体験のない学生は、シミュレーション演習に取り組む当初、普段の自分(一般人)の発想、感覚で取り組み始めます。学生は、シミュレーション演習中の模擬患者とのやり取りで困ったり、悩んだりした体験を乗り越えていく中で、臨床の厳しさやリアルを感じるとともに、援助者として実践するということを実感し、専門職としての意識化につながっていくのだと話されました。「一般人から専門職者へ」、とてもインパクトのある表現でした。ファシリテーションにおいては、教員が喋りすぎないようにすることで意見を出しやすくすることや学生の反応の中から生まれてくる学びを大事にされていました。教員は、学生がとった行動が適切な思考を伴ったものであるのかを確認するなど、行動の背景にある学生の思考へのアプローチが必要だと話されました。実践されている具体的な内容を織り交ぜて話題提供していただき、看護職として成長していく上で、基礎看護学教育の重要性を再認識できました。
話題提供後に、参加者間でシミュレーション教育の取り組み状況や課題などの意見交換を行いました。「学生が目標と全く違う行動をしたときには、どうしてそう考えたのかを確認する」「学生が間違いやすい内容を共有し、誰もが考えたかもしれない間違いであることを伝えながら答えを提示するように努めている」等、学生を安心させ、緊張感をほぐせる環境づくりに努めている点が特に多く聞かれました。また、ファシリテーションガイドは大切なツールですが、「準備しても何が起こるかわからない」「形を作りすぎると、学生の着眼点を見逃したり、意見の膨らみを止めてしまったりするのではないか」などの意見もありました。伊藤先生からは、学生に期待する動きと、教員が気にかけておくべき動きを決めておく必要があるというアドバイスをいただきました。また、「教員間で共有していても客観的に見れば学んでいる内容が異なる場合があり、教員個々の教育観の違いが要因ではないか」との意見も提示されました。教員間での考え方の統一の難しさを感じるとともに、教員のファシリテーションのレベルを整えることも重要ではないかという意見もありました。
ICTやVRの発展によりシミュレーション教育は更に進化すると考えられます。看護学生が一般人から看護専門職者へと成長するための一教育方法としてシミュレーション教育がとても有益であると感じました。また、参加者のみなさんと情報交換できたことでブラッシュアップのヒントが得られた有意義な時間となりました。ご参加いただきました皆さまありがとうございました。